画像を追加・更新した 再度画像を追加した 拡大画像
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
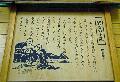 |
| JR羽越本線の吹浦(ふくら)駅から、海辺の国道を海を左に見ながら 1kmほど歩くと海岸の岩場に釈迦三尊像・羅漢像など 22体が厚肉彫りされている。 吹浦は、もともと漁村だったところで多くの漁師が日本海の荒波に命を失ってきた。 地元・海禅寺の 21代住職 寛海和尚が海難者供養と海上安全を発願し、明治元年まで 5年の歳月をかけ 22体の磨崖仏を刻んだと伝えています。 厳しい日本海の荒波や風雪にさらされ風化は激しいが、奇岩に打ち寄せては砕ける波濤に尊者、羅漢さんはやさしく微笑んでいた。 いま、この国には収監されている尊師もいるが、先日の新聞には 「高裁が控訴を棄却、死刑判決確定の可能性高まる」 の文字が躍っていた。 この十六羅漢岩は、「未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選」 に選ばれたとか。 十六羅漢岩から駅に戻る途中にある、出羽二見と呼ばれている夫婦岩もスバラシイ景観です。 両岸に掛けられたしめ縄に霞のかかった夕日が覗いていた。 初秋の頃車で再訪、数時間滞在した。 梅雨明け直後再々訪した。 国典に入選、梅雨明け直後再々再訪した。 |