| 出羽三山 山形県庄内地方の名峰月山(標高1,984m)と、その峰々に広がる羽黒山・湯殿山の総称で、山岳修験の山として古くから広く知られている。 上記 出羽三山の月山頂上に月山神社、羽黒山頂上に出羽神社、湯殿山中腹に湯殿山神社が各々鎮座しており、この三神社を通称出羽三山神社と呼んでいる。 三山はかつて三所権現ともいわれ、羽黒山が里宮(観音菩薩)、月山が本宮(阿弥陀如来)湯殿山が奥の院(大日如来)と位置づけ独立した神社であった。 この地方の冬は積雪が深く、月山や湯殿山は人里を離れており冬季の参拝奉仕は無理でした。 月山・湯殿山両神社の里宮として出羽神社に三神を合祭した「三神合祭殿」での参拝となります。 恒例の祭典も三神社同時に合祭殿で行っているようです。 この三山は、今から1,400年程前 蜂子皇子 の開山と伝えており、古代からの山岳信仰と密教が融合し山伏の行場として信仰を集め全国に広まった。 この三山を駆けめぐり、難行・苦行の登拝を通して己の心身を鍛える修行を羽黒修験では「三関三渡」 と呼び 「羽黒・月山・湯殿」 への移動は 「現在・過去・未来」 という精神的な意識が行き来するのだとか?。 今でも一週間以上にも及ぶ山駆けなどの荒行「秋の峰入り」が行われており、年々増える参加者は抽選で決める程の人気だとか。 ここは、神仏習合の聖地でしたが明治の「神仏分離令」で神社となった、しかし、いまだに仏教色が色濃く残っている。 羽黒山頂上の出羽神社境内には多くの摂社や末社が点在していますが、その中で普通の神社にはない鐘楼と大鐘が、そして線香が匂う霊祭殿近くには卒塔婆が、さらに表参道杉並木の中に五重塔(国宝)がひっそりと立っており「神仏習合」の名残?をとどめています。 今回の旅は、出羽神社の石仏を撮り 湯殿山にお詣り?して帰る予定でした。 湯殿山で御神体巡拝をしていたとき、なぜか三山詣りをしてから帰ろうと強い意志?が湧いてきた。 延泊し 三山詣りは成就したのだが、参拝順が............ 出羽三山神社発行の冊子 「出羽三山」 によると、三山の登拝は、先ず郷里の行屋の精進潔斎から始まる。 身も心も清め、白の浄衣をつけ、木綿注連をかけ、清浄な姿で数十里の道を出羽三山に運ぶのである。 かくして山麓の宿坊や、羽黒山頂の斎舘に一夜の参籠を遂げ、羽黒の本社に詣で、神楽や祈祷を捧げ、山先達の導くままに 「あやに、あやに」 の神文を唱え、又 「六根清浄」の掛念仏で、拝所拝所を駆ける。 麓から山巓へ山頂から渓谷へと巡拝、月山本宮を拝し、湯殿山本宮に詣でるのである。 と記している。 |
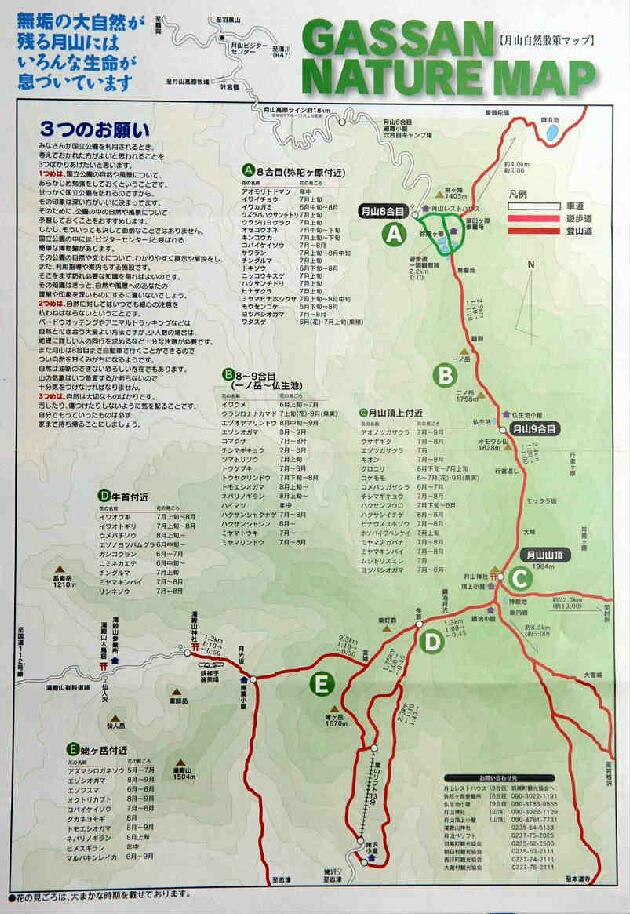 |